脳神経外科
脳神経外科の特色
脳の病気は生命の危険に直結するため、治療には高い専門性が要求されます。現在、当科では脳神経外科学会認定脳神経外科専門医6名、専門医を目指す専攻医1名および卒業1、2年目の初期研修医からなるチームで治療に臨んでいます(2025年5月現在)。
専門医の6名は全般的な脳神経外科的診療技術に加え、それぞれが脳腫瘍、脳血管障害、脳血管内治療、頭部外傷、画像診断などの専門分野を担っています。特に脳神経外科手術では、顕微鏡を用いて行う開頭手術とともに、カテーテルによる脳血管内治療が年々進歩しています。当科では3名の脳血管内治療専門医が在籍しており、複数の選択肢の中から患者さん一人ひとりに合った治療を提案します。
当院における脳疾患治療のもう一つの特色は、脳神経外科医だけでなく、リハビリ科や内科の医師、看護師、リハビリスタッフ、薬剤師、ソーシャルワーカーなど多職種から成る「脳疾患センター」を組織していることで、患者さんの早期社会復帰に向けて、一丸となって取り組んでいます。
一次脳卒中センターコア施設認定について
当院は2019年9月に、日本脳卒中学会から一次脳卒中センター(PSC)に認定され、さらに2020年10月からは、血栓回収療法を実施できないPSCから同療法を必要とする患者さんを常時受け入れるPSCコア施設として認定されています。
PSCコア施設の認定には、脳神経血管内治療医あるいは脳血栓回収療法施行医が合計3名以上在籍、血栓回収療法を年間12例以上実施、24時間/365日血栓回収療法に対応可能、脳卒中相談窓口の設置などの要件があり、これらを全て満たす施設が認定されます。
岡山県内では、3病院のみがPSCコア施設に認定されており、特に岡山市を含む人口90万人超の岡山県南東部医療圏では当院が唯一の認定施設です。脳卒中相談窓口も2022年度に立ち上げ、当院で治療した患者さんの療養や福祉サービスに関する相談にあたっています。今後もPSCコア施設としての役割を果たせるよう、地域における脳卒中医療と介護の体制整備に尽力して参ります。
(2025年5月現在)
関連リンク
▼脳疾患センターに関する記事が掲載されています 北長瀬の風Vol.27
▼外部リンクにつながります日本脳卒中学会
一次脳卒中センター
(PSC)コア認定について
診療内容
上記以外にも脊椎脊髄疾患、頭部外傷、高血圧性脳出血など、この欄で説明しきれなかった多くの脳疾患があります。当科での診療を希望される方は、かかりつけ医にご相談の上、病状や基礎疾患について情報提供をいただければ、より速やかに診断、治療を進めることが可能です。
くも膜下出血(破裂脳動脈瘤)
くも膜下出血(SAH)の多くは、脳血管分岐部にできた脳動脈瘤が破裂して生じます。SAHを生じると、急激な脳圧の上昇や血腫による脳の損傷により、急性期に半数近くの方が命を落とされます。出血が軽い場合には社会復帰も可能ですが、再出血を生じると神経症状が著しく悪化するため、破裂脳動脈瘤に対しては、早期に再破裂防止の治療を行う必要があります。
破裂脳動脈瘤の治療には、開頭クリッピング術とコイル塞栓術の2つの方法があります。いずれも動脈瘤への血流を遮断することが目的で、クリッピング術は開頭して脳の溝を剥離して動脈瘤に到達し、瘤をクリップで閉じる手術で、一方、コイル塞栓術は動脈瘤の中にカテーテルを誘導して、柔らかいコイルを瘤内に詰める手術です。当科ではいずれの方法についても豊富な治療経験を有しており、患者さんによって適した方法を選択します。
クリッピングやコイリング後には、くも膜下出血後の合併症にも注意が必要です。肺や心臓などの機能異常、血管が細くなり脳梗塞を惹起する脳血管れん縮、髄液循環障害による水頭症を生じる危険性があり、これらも乗り越えられるよう治療を進めます。
開頭術によるクリッピング

コイル塞栓術

未破裂脳動脈瘤
未破裂脳動脈瘤は、まだ破れていない状態の脳動脈瘤であり、脳ドックのMRIで発見される方もいます。発見された場合、造影CTやカテーテル検査を行い、患者さんの背景条件や動脈瘤の部位・サイズ・形状などを鑑みて、手術の必要性を判断します。
我が国の未破裂脳動脈瘤調査では、3mm以上の大きさの未破裂脳動脈瘤の年間破裂率は0.95%で、特に大きいものや特定の部位にある動脈瘤では、破裂率が高めであることがわかりました。このため治療の必要性と安全性が比較的高いものであれば破裂前の手術をお薦めし、一方、破裂の危険性が低いものは治療せずに経過をみています。経過をみる場合でも、定期的にMRIや造影CT検査を行い、サイズや形状が変化した際には、手術を考える場合もあります。
手術は開頭クリッピング術かコイル塞栓術かのいずれかを選択します。多くの方は無症状であり、手術は予防的なものですので、治療には高い安全性と確実性が要求されます。当科では未破裂脳動脈瘤に対するクリッピングの際には、術中蛍光血管造影や脳刺激誘発電位測定を用いて合併症の回避に努めます。またコイル塞栓術ではバルーンカテーテルや脳血管ステントなどの補助的デバイスを適宜用いて行います。
さらに2021年からは脳動脈瘤に対する新しい治療法であるフローダイバーター留置が、また2025年からは袋状の塞栓デバイスであるWoven EndoBridgeデバイス(WEB)が当院で施行可能になっています。
ステントを併用した未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術

急性期脳梗塞
脳梗塞は、脳血管が細くなったり、心臓にできた血栓が脳に飛んだりすることで、脳血管が詰まる病気です。麻痺やしびれ、言語障害(言葉がでない、呂律が回らない)、視力視野障害、計算力低下、めまい、複視、認知機能低下などの梗塞の場所により異なった症状を生じます。
脳梗塞治療の大きな転機は2005年の血栓溶解剤t-PAの登場でした。t-PAを静脈投与すると詰まった血栓を溶かして再開通させ、脳梗塞の拡大を抑え後遺症を軽減させます。但しt-PAは切れ味が鋭い分、逆に出血を起こして症状を悪化させる危険性があります。そのため発症から4.5時間以上経った人、最近大きな手術を受けた人、既に抗凝固剤がよく効いている人などには投与できません。また投与できても再開通しないこともまれではありません。
そこでカテーテル手術への期待が高まり、2010年以降、t-PA治療の非適応例・無効例に対して血栓回収用カテーテルの使用が認可されました。さらに2014年にはステント型血栓回収機器が導入され、治療の有効性、安全性がさらに高まりました。当科はカテーテル手術による血栓回収療法に関し、豊富な経験数を重ねています。2018年以降には血栓回収療法の適応時間が延長されたり、画像所見によっては発症時刻不明例へのt-PA投与が可能になったり、さらにその後も広範囲脳梗塞例や後方循環閉塞例にも適応が拡大されるなど、益々高度な専門的知識が求められるようになっています。
再開通療法後も抗血栓剤の内服を続けます。また慢性期に脳血流不全状態が残り、脳梗塞再発の危険性が高い患者さんには、バイパス術やバルーンカテーテルによる拡張術を行うこともあります。
治療前(矢印が閉塞した右中大脳動脈)

ステント型機器と改修した血栓(矢頭)

再開通後

頚動脈狭窄症
頚動脈狭窄症は、頚部内頚動脈にプラークと呼ばれる動脈硬化(アテローム)を生じ、プラーク内のコレステロールや血栓が脳に飛んだり、狭窄のために血流が低下したりすることで、狭窄側の視力障害や狭窄と反対側の神経学的巣症状を来たします。症状は短時間で回復することもあれば、脳梗塞となり残存する場合もあります。回復した場合でも油断せず、直ちに脳神経外科施設を受診して精査治療を開始することが大切です。最近では脳ドックにおいて無症状の段階で発見される場合もあります。
MRIやエコーで頚動脈狭窄症と診断されたら、さらに造影CT、脳血流SPECT検査、脳血管造影、心臓検査などを行います。その結果、手術が不要と判断された場合でも、抗血小板剤内服や生活習慣病の管理といった内科的治療が必要で、MRIや頚動脈エコーなどの定期的検査を続けます。
症状のある患者さんや無症状でも狭窄の程度が強い患者さんには手術を行います。方法としては頚動脈内膜剥離術(CEA)と頚動脈ステント留置術(CAS)の2つがあります。CEAは頚動脈を露出して切開し、プラークのたまった内膜部分を剥離摘出します。一方、CASはカテーテル手術の一つで、血管の中からメッシュ状の金属の筒であるステントを留置し、プラークとともに血管内腔を拡げて平滑化する方法です。当科ではいずれの方法も数多く行っています。
アテローム

CEA

CAS

脳動静脈奇形
脳動静脈奇形(AVM)は、脳血管の一部にみられる生来の異常で、毛細血管が欠損し、動脈血が直接静脈側に注ぐ短絡状態(短絡部の血管の集まりをナイダスと呼びます)となった病気です。過大な圧が静脈側にかかることによって脳内出血を生じます。未破裂AVMの年間出血率は2%〜数%で、一度破裂したAVMの出血率はより高くなります。出血以外には、けいれん発作を生じたり、周囲の脳へ供給される血液がAVMに盗られることによって、麻痺やしびれ、認知機能の低下を生じたりする場合もあります。他の原因による脳卒中よりも若い年代で発症します。
AVMが見つかった場合、治療を行うべきかどうか、治療するとすればどの方法がよいかに関しては、患者さんの年齢や症状、出血の有無、AVMの場所や大きさ、治療の危険性などにより判断します。適切な治療方針提案のためにはMRIやCT、脳血管造影などの検査を行う必要があります。
AVMの治療は、1)開頭によるナイダス摘出術、2)カテーテル手術、3)放射線治療(ガンマナイフ、サイバーナイフ)の3つに大きく分けられ、いずれかの単独の方法で、あるいは複数の方法を組み合わせて治療を行います。

もやもや病
もやもや病は内頚動脈が脳底部で進行性に狭窄する病気です。脳への血流が減少するため、脳底部の本来細い穿通枝が代償性に発達し、これが脳血管造影で煙が「もやもや」と立ち上るように見えることからもやもや病と呼ばれるようになりました。
もやもや病で血管が狭窄する機序は十分には解明されていませんが、最近の報告では遺伝子異常の関与が示唆されています。発症時期は10歳以下と30~40歳台に2つのピークがあります。小児期の典型的な症状としては、過呼吸などで脳血流不全が一時的に悪化し、麻痺やしびれ、言語障害などのTIAを生じます。成人ではTIA・脳梗塞以外に半数が頭蓋内出血で発症します。脆弱なもやもや血管に負担がかかることで出血すると考えられています。
脳虚血発作がみられる場合には血行再建術(バイパス術)をお薦めします。手術を行うことで、発作を減らし、将来の脳卒中の危険性を下げる効果が期待できます。
当科では、頭皮の血管を脳表血管に吻合する直接バイパスと、脳表に筋肉などを接着させ、根が成長するような脳への新生血管の発達を促す間接バイパスを組み合わせた複合的血行再建術を行っています。

脳腫瘍 (良性、悪性)
髄膜腫、聴神経鞘腫、血管芽腫、下垂体腺腫などの良性腫瘍に対しては、脳と神経の機能を温存しつつ再発を防止する治療を心懸けています。必要に応じて術前栄養血管塞栓術を行い、術中には手術用ナビゲーション(光学式、磁場式)神経モニタリング、神経内視鏡、頭蓋底手術手技などを駆使して摘出します。
膠芽腫に代表される悪性腫瘍に対しては、術中に蛍光診断 (化学的ナビゲーション)を行って腫瘍を出来るだけ摘出し、抗がん剤ウェハースの脳内留置を行います。術後には化学療法剤テモゾロミドや分子標的薬ベバシズマブを用いた後療法を行い、放射線療法の併用も検討します。悪性リンパ腫に対しては、手術摘出標本で診断を確定し、当院血液内科医と連携して、メソトレキセートなどによる化学療法を行います。

片側顔面けいれん・三叉神経痛
片側顔面けいれんは、顔の半分が意思と関係なくぴくぴくするもので、目の周囲から始まり口元へと広がります。三叉神経痛は食事や歯磨きなどの際に、片側顔面に電撃痛を生じるものです。症状の原因は、いずれも神経が脳からでる部分に血管が当たり刺激を与えていることです。
治療として、耳の後ろに小さな開頭を行い、血管による神経の圧迫を解除する微小血管減圧術が著効します。手術以外の方法として、顔面けいれんではボツリヌス毒素の筋肉注射を、また三叉神経痛では薬の内服や定位的放射線治療、神経ブロックなどを行う場合もあります。


正常圧水頭症
水頭症は、頭蓋内で産生される髄液の流れや吸収が妨げられ、髄液が溜まって拡大した脳室が脳を圧迫し、認知症、歩行障害、尿失禁を来す病気です。高齢者にみられる原因不明のものを特発性正常圧水頭症(iNPH)と呼びます。
CTやMRIでiNPHが疑われたら、腰椎穿刺で背中から髄液を抜いて症状が改善するかどうかを判定するタップテストを行います。
改善が期待される場合には髄液シャント手術を行います。当科では頭蓋骨に穴をあけ、脳室から腹腔までの皮下にチューブを通す脳室腹腔シャント術か、腰椎髄液腔から腹腔までの皮下に通す腰椎腹腔シャント術のいずれかを選択しています。髄液の流れ過ぎや排出不足を回避するために、体外から圧の変更ができる圧可変式バルブをチューブの途中に介在させます。
MRI

シャント手術

手術用機器のご紹介
当院では、2023年5月に新しく手術顕微鏡と手術用ナビゲーションを導入しました。
手術顕微鏡 KINEVO900

脳神経外科手術を肉眼のみで行うのは不可能で、1mm以下の精度が要求される操作には、手術用顕微鏡の助けが必要になります。
今回導入した手術顕微鏡(カールツァイス社製)は、高倍率で術野は明るく見え、振動を最小限に抑えるアクティブ制振機構の搭載により、画面の揺れもとても小さくなりました。
また、脳の組織や血管などを外視鏡モードで4Kモニターに映し出し、3Dゴーグルを着用すれば、立体視しながら手術を行うことが可能です。手術にかかわるスタッフ全員が映像を共有できるので、スタッフの教育面でも効果が期待できます。
さらに、腫瘍観察モジュールの搭載により、顕微鏡のモードを切り替えると、悪性腫瘍や血液が流れている部分が光って見えます。これらの機能によって、血管や正常な脳を傷つけることなく、腫瘍の取り残しの有無を確認しながら、摘出手術を行うことが可能になりました。
手術用ナビゲーション StealthStation S8

手術用ナビゲーションシステム(メドトロニック社製)は、脳内部の位置情報を画面に表示するシステムです。手術用顕微鏡と連動させることで、術前に取り込んでおいたCTやMRIの画像情報が、術中の画像に重ね合わせて表示されます。この機能によって、脳腫瘍などの範囲を顕微鏡で確認できます。また、ポインターによって脳内のどの部分に触れているかを確認できるため、脳の深部にある脳腫瘍を摘出しやすくなりました。

顕微鏡とナビゲーションシステムの2つを連動することで、脳腫瘍手術の精度が向上し、より安全で確実な治療が期待できます。
メディア掲載情報
山陽新聞朝刊 岡山医療健康ガイド「MEDICA(メディカ)」ならびにそのWEBサイトで、手術顕微鏡とナビゲーションシステムに関する記事が掲載されました。徳永副院長と渡邊主任部長がコメントをさせていただいています。こちらもぜひご覧ください。
▼岡山の医療健康ガイドMEDICA 「脳神経外科に最新顕微鏡とナビゲーションシステム」(2023/7/17記事)「脳神経外科に最新顕微鏡とナビゲーションシステム」
実績(2024年度)
手術件数
295件
主な手術の内訳
(単位:件)
| 直達手術 (194) |
脳動脈瘤開頭クリッピング | 13 |
| 開頭脳内血腫除去 | 13 | |
| 脳腫瘍摘出術 | 4 | |
| 急性硬膜下・硬膜外血腫除去 | 9 | |
| 頚動脈内膜剥離術 | 8 | |
| 慢性硬膜下血腫穿頭術 | 80 | |
| 脳血管内手術 (101) |
脳動脈瘤コイル塞栓術・フローダイバータ留置 | 33 |
| 血栓回収療法 | 49 | |
| 頚動脈ステント留置術 | 11 | |
| 脳動静脈奇形・硬膜動静脈瘻塞栓術 | 5 |
手術以外
| 超急性期脳梗塞に対するt-PA静注療法 | 25 |
スタッフ紹介
理事長
松本 健五 Kengo Matsumoto
副院長
徳永 浩司 Koji Tokunaga

出身
昭和63年
岡山大学医学部卒
専門
脳血管障害、脳卒中
血管内手術
| 資格 |
|---|
| 日本脳神経外科学会脳神経外科専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会脳血管内治療専門医・指導医 日本脳卒中学会脳卒中専門医・指導医 日本脳卒中の外科学会技術指導医 日本心血管脳卒中学会学術評議員 岡山県脳卒中連携体制検討会議委員 岡山大学医学部医学科臨床教授 臨床研修指導医 |
| 記事・コラムなど |
|
岡山の医療健康ガイドMEDICA 地域包括ケア時代の新しい急性期医療 岡山の医療健康ガイドMEDICA 医療アラカルト 岡山の医療健康ガイドMEDICA 市民に新時代の医療を |
統括診療部長/入退院管理支援センター長/救急センター長
桐山 英樹 Hideki Kiriyama

出身
平成6年
岡山大学医学部卒
専門
脳血管障害(脳卒中)
脳の画像診断
頭部外傷
| 資格 |
|---|
| 日本脳神経外科学会日本脳神経外科専門医 日本救急医学会救急科専門医 日本脳卒中学会脳卒中専門医 日本頭痛学会頭痛専門医 JATECインストラクター JPTEC世話人 ISLSディレクター MCLSインストラクター 岡山大学医学部医学科臨床教授 臨床研修指導医 日本DMAT隊員 共用試験実施評価機構OSCE認定評価者 |
主任部長
渡邊 恭一 Kyoichi Watanabe

出身
平成10年
岡山大学医学部卒
専門
脳神経外科一般
血管内手術
| 資格 |
|---|
| 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会専門医 ISLSファシリテーター 臨床研修指導医 |
| 記事・コラムなど |
主任医長
髙杉 祐二 Yuji Takasugi

出身
平成20年
岡山大学医学部卒
専門
脳神経外科一般
血管内手術
| 資格 |
|---|
| 日本脳神経外科学会脳神経外科専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会脳血管内治療専門医 日本脳卒中学会脳卒中専門医・指導医 日本脳卒中の外科学会技術認定医 ISLSファシリテーター 臨床研修指導医 |
| 記事・コラムなど |
医長
岡 哲生 Tetsuo Oka
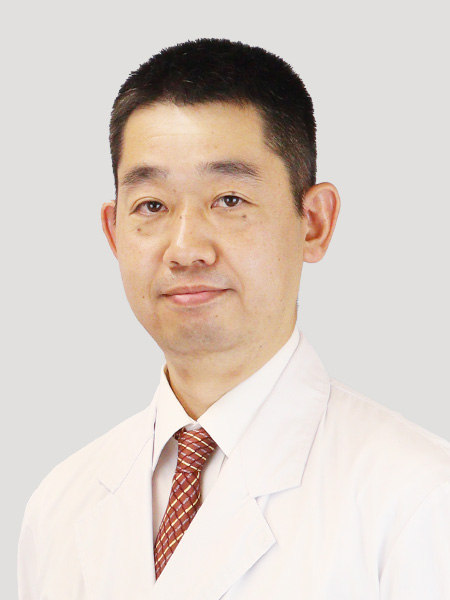
出身
平成20年
岡山大学医学部卒
専門
| 資格 |
|---|
| 日本脳神経外科学会脳神経外科専門医 日本脳卒中学会脳卒中専門医 日本脳神経血管内治療学会脳血栓回収療法実施医 日本脳神経血管内治療学会脳血管内治療専門医 臨床研修指導医 医学博士 |
医長
服部 靖彦 Yasuhiko Hattori

出身
平成20年
香川大学医学部卒
専門
| 資格 |
|---|
| 日本脳神経外科学会脳神経外科専門医 日本救急医学会救急科専門医 臨床研修指導医 日本DMAT隊員 |
医員
田村 駿 Shun Tamura

出身
令和4年
鳥取大学医学部卒
専門
医師
井上 智 Satoshi Inoue

出身
平成13年
岡山大学医学部卒
専門
脳神経外科一般
脳腫瘍
| 資格 |
|---|
|
日本脳神経外科学会脳神経外科専門医・指導医 |
医師
梅田 剛志 Tsuyoshi Umeda

出身
平成30年
岡山大学医学部卒
専門



