万が一のとき重症化させないために
はじめに
ようやく夏も盛りを過ぎて、ますますお元気にお暮らしのことと存じます。今回は「感染症と抗リウマチ薬」というテーマについてです。関節リウマチのお薬の中には、免疫機能に影響を及ぼす作用をもつものがあり、お薬を使用することで結核、肺炎、敗血症などの重篤な感染症にかかるリスクがあります。安全に治療していくために、さまざまな検査を行ったり、ワクチン接種が必要になる場合があります。
●どんな検査が必要なの?
血液検査
関節リウマチのお薬を使用することで、血液の成分に影響をおよぼす可能性があります。好中球数、リンパ球数、ヘモグロビン値などに減少がみられた場合には、お薬をお休みすることもあります。
B型肝炎ウイルス検査
HBc抗体またはHBs抗体陽性の方に免疫機能に影響を及ぼすお薬を使用すると、B型肝炎ウイルスの再活性化がおこる可能性があります。治療をはじめる前、またお薬を使用中にも必要に応じて検査を行います。
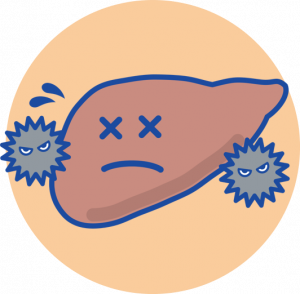
結核スクリーニング検査
胸部画像検査で結核を疑われる方、結核の治療歴のある方、インターフェロンガンマ遊離試験やツベルクリン反応検査などにより、過去に結核の感染があったことを疑われる方、身近に結核の患者がおられる方では、治療をはじめる前に抗結核薬を使用する場合があります。
治療中に使用できるワクチン、使用できないワクチン
生ワクチンは、生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもの(弱毒化病原体)を接種します。関節リウマチのお薬の中には、お薬を使用する直前やお薬の使用中に、生ワクチン接種ができないものがあります (メトトレキサートやタクロリムス、生物学的製剤、JAK阻害薬などを使用している方)。
免疫を抑えている状態では、ワクチン接種をしても期待される免疫効果が得られず、有効性が低下するおそれがあるとされています。また、生ワクチンに含まれる弱毒化病原体が制御不能になり、病原体による感染症(ワクチン関連疾患)を引き起こす可能性があるため、生ワクチンを接種することができません。
生ワクチンの接種ができない一方、不活化ワクチンについては関節リウマチのお薬を使用中の方も接種がうけられます。関節リウマチの患者さんがワクチンを接種する場合、免疫を抑える作用のあるお薬の影響を受けにくいタイミングを選ぶことがあります。通常ワクチン接種は、治療を始めるまえ、またはお薬の使用を一時的に中断したあとに行うことが推奨されます。接種が適切かどうかを慎重に確認する必要があるため、自己判断での接種は避け、必ず医師と相談したうえで接種を行いましょう。
不活化ワクチンであるインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンについては、日本リウマチ学会からも積極的な投与を推奨されています。ワクチン接種後に、発熱や倦怠感が現れる場合があり、数日で改善しますが、重篤な症状が出た場合はすぐに医師に相談しましょう。
非生ワクチンの例
インフルエンザHAワクチン
接種すればインフルエンザに絶対にかからない、というものではありませんが、インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています。毎シーズン原則1回接種します。
ニューモバックスNP
肺炎球菌という細菌によって引き起こされる重症な肺炎などにかかることを予防します。肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、定期接種で使用されるニューモバックスNPは、この23種類の血清型の侵襲性肺炎球菌感染症を4割程度予防する効果があります。
シングリックス
水痘帯状疱疹ウイルスに対する免疫力を高め、帯状疱疹の発症を予防します。また、帯状疱疹後神経痛と呼ばれる、帯状疱疹が治った後も長 く続く痛みを予防します。水痘帯状疱疹ウイルスワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンがあり、接種の回数・効果・費用が異なります。
シングリックスは不活化ワクチンであり、免疫を抑える作用のあるお薬を使用している方も接種をうけられます。通常2~6ヶ月の間隔をあけて2回接種します。

新型コロナワクチン
令和6年度から、65歳以上の方と60~64歳の一定の基礎疾患のある方は、新型コロナワクチン定期接種の対象となりました。定期接種のスケジュールは毎年秋冬に1回行うこととしています。定期接種で承認されている新型コロナワクチンは全部で5種類、大きくmRNAワクチンと組換えタンパクワクチンにわけられますが、どのワクチンにも一定の感染予防、重症化予防の効果があるとされています。
日常的に感染症対策を
お薬を使用することで感染症のリスク等が高まるため、感染を疑う症状(発熱、悪寒、咽頭痛)や、貧血を疑う症状(顔色が悪い、疲れやすい、頭痛、動悸、息切れ)がみられた場合には、病院に連絡するようにしましょう。
また過去に感染症にかかったことのある方は、治療をはじめると重篤化するおそれがあるため、あらかじめ対策しておくことも重要です。手洗い・うがい、マスクの着用、人ごみを避ける等の感染対策をいつも以上に心がけましょう。
岡山市立市民病院 薬剤部 菊岡 奈緒
参考文献
- B型肝炎治療ガイドライン
- 日本リウマチ学会
- 予防接種ガイドライン2024年度版
お話をお伺いしたのは・・・
岡山市立市民病院 薬剤部 菊岡 奈緒
市民病院HP リウマチセンター当院リウマチセンターについては、こちらからご覧ください。
市民病院HP リウマチ教室(記事一覧)リウマチ教室の記事のアーカイブもございます。ぜひご覧ください。
※役職は掲載時のものです。変更になっている場合がありますがご了承ください
市民病院で20年以上にわたり行ってきたリウマチ教室。新型コロナウイルスの影響により、2020年7月よりWeb版・瓦版(院内での資料配布および掲示)と形態を変え、皆様のリウマチ療養にお役立ていただくべく、引き続き情報を発信しております。
※更新日が古いものは最新の知見と異なる場合がありますのでご注意ください。

